昭和12年に、北九州の貧村の娘である、秋子、道子、ユキ、梅子らは、家のために1000円で買い集められました。
秋子の恋人である正夫が北支へ出征することになりましたが、ひろ子の取計いで2人は会うことができます。
昭和13年、彼女達は九江に行き、その中には朝鮮人の金子もいました。
慰安所で多くの兵隊の相手をして、梅子、道子、ひろ子は数日で前借金を返済してしまう程でしたが、兵隊や国の為に居残ることにしました。
慰安婦は更に前線に送られ、そこで秋子は正夫と再会し、2人は激しく燃えるのです。
しかし、中国軍の激しい攻撃を受けて、正夫が撃たれ、正夫にしがみついた秋子も殺されてしまう、というストーリー。
この映画「従軍慰安婦」が、ソフト化されることなく封印作品となっているのは、別に歴史問題が理由ではありません。
タイトルとなった「従軍慰安婦」という言葉が原因なのです。
事実、この映画は、いわゆる「強制連行」や韓国人慰安婦を取り上げるといった社会派ではありませんでした。
当時、東映が売り出していた鳴り物入りの若手美人女優の中島ゆたかありきの企画で、1971年にミス・パシフィックで日本代表となった中島のエキゾチックな魅力を存分に発揮させるべく慰安婦を演じさせたにすぎません。
明日をも知れぬ兵士と、戦地の遊女の悲恋がテーマ。
その証拠に脚本には「網走番外地」シリーズや東映ポルノ路線を手がけていた石井輝男を起用しています。
くり返しますが、映画の内容が問題で封印されているわけではないのです。
じつは「従軍慰安婦」という用語は政府の公式な名称ではありません。
1973年、毎日新聞の記者であったジャーナリストの千田夏光(かこう)が命名して広まった造語。
千田の著書「従軍慰安婦”声なき女”八万人の告発」(双葉社)は、この映画の原作にもなっています。
この著書がのちの従軍慰安婦問題を引き起こしていくわけですが、発表当時は、タイトルのキャッチさが話題となりました。
たしかに従軍カメラマン、従軍看護婦にくらべ、「従軍と慰安婦」のミスマッチ感によるインパクトは大きく、文句なしのタイトルといえるでしょう。
当然、 東映も 「従軍慰安婦」という言葉を使いたがりました。
そのため、千田夏光から映像化権を買い取ったにすぎず、別に著書の中身はどうでもよかったのです。
とはいえ、1985年以降、この千田夏光の著作内容は、多くの専門家から間違いが指摘され、2014年、朝日新聞が異例の全面撤回をする「吉田証言」のベースともなりました。
そんな問題作を原作にしている以上、ソフト化すれば保守層からあらぬ批判を受けかねないというわけです。
2015年、「月刊シナリオ」9月号で「従軍慰安婦」の石井輝男の脚本が掲載になりました。
千田の著書とは関係ないという、せめてもの意思表示なのかもしれません。
Sponsored Links

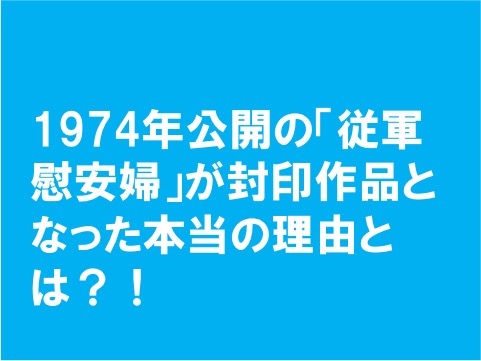
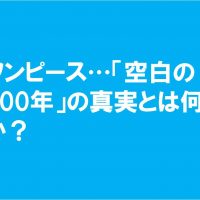
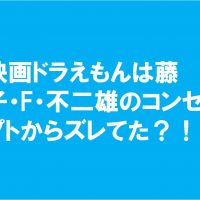
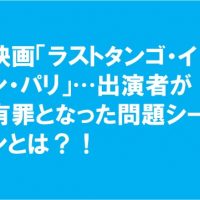
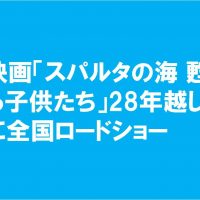
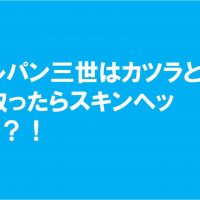
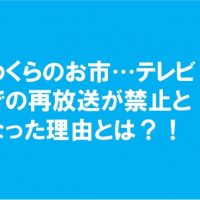
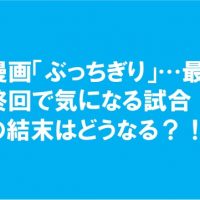
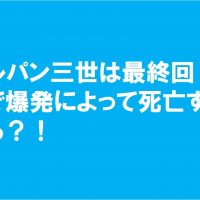
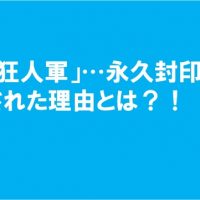

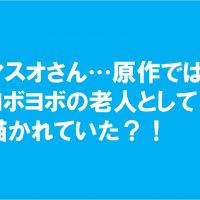
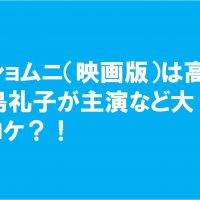
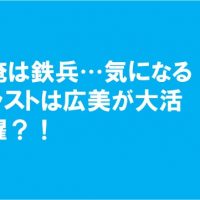
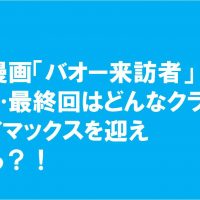
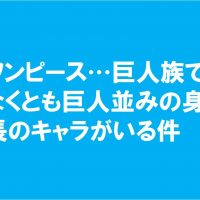
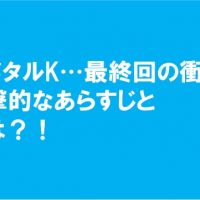
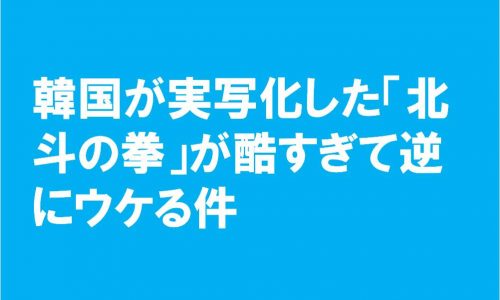
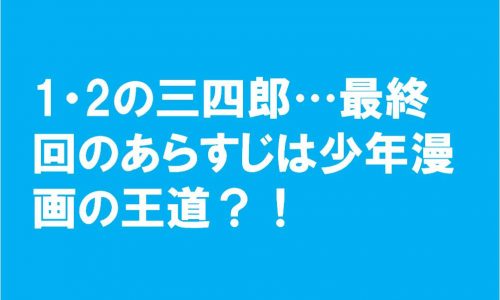
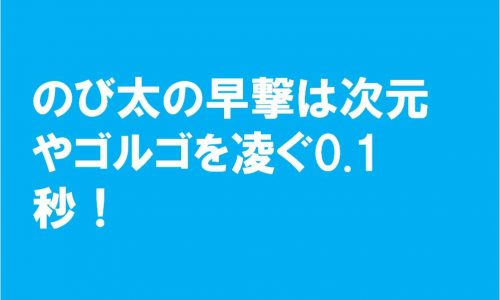
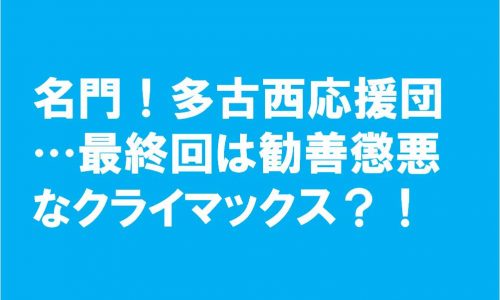
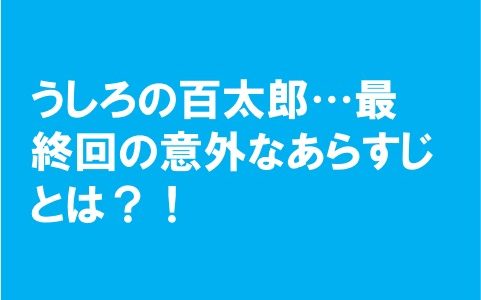
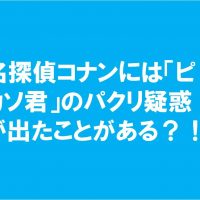
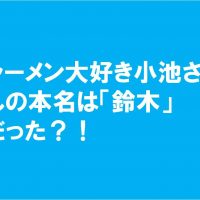
この記事へのコメントはありません。